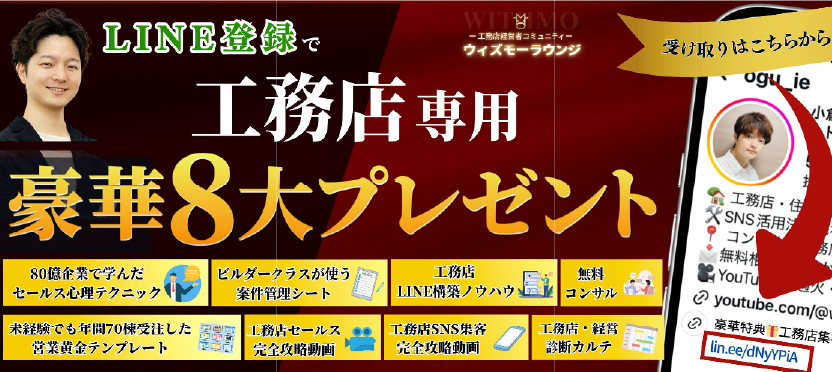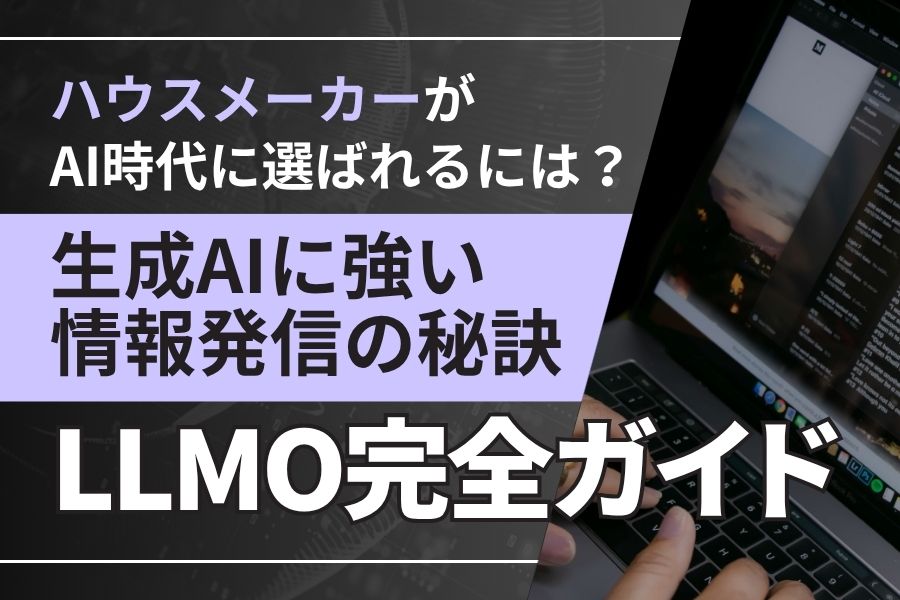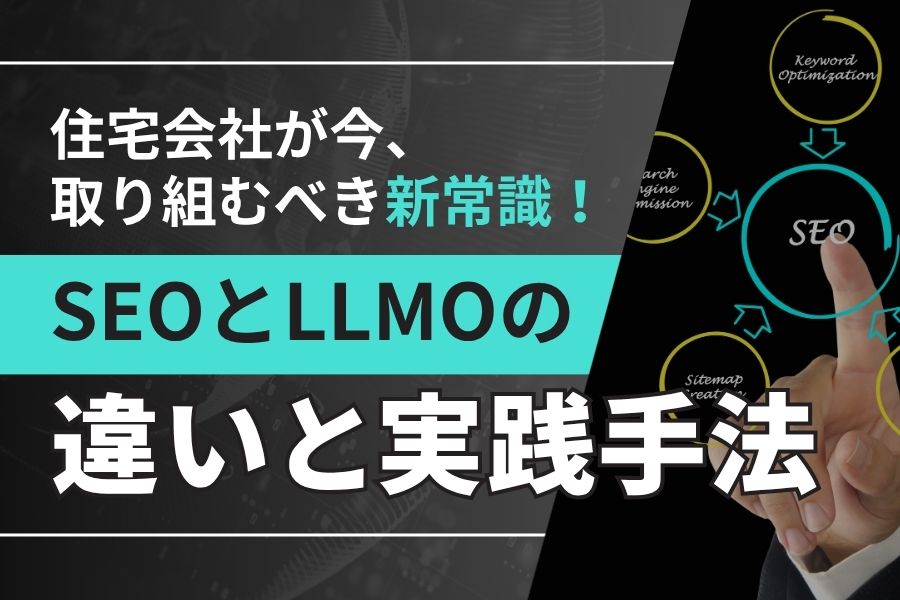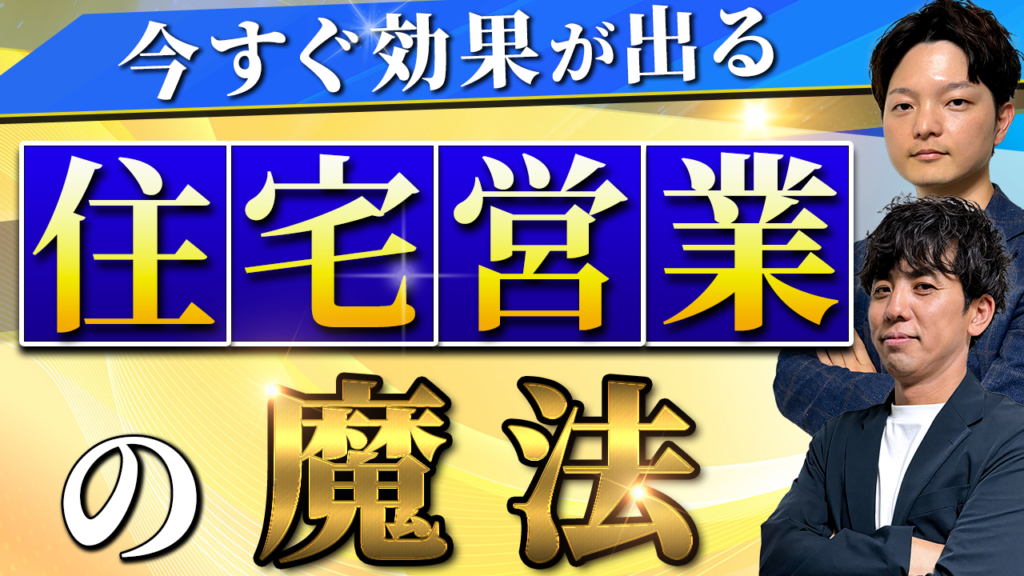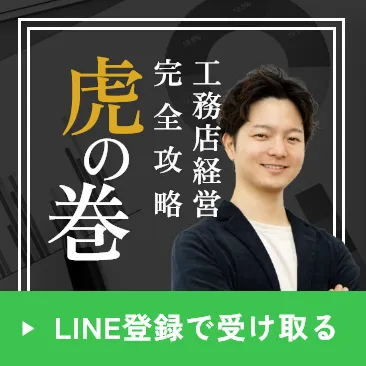工務店経営完全攻略ロードマップ!集客から受注・現場・SNS・組織づくりまで徹底解説
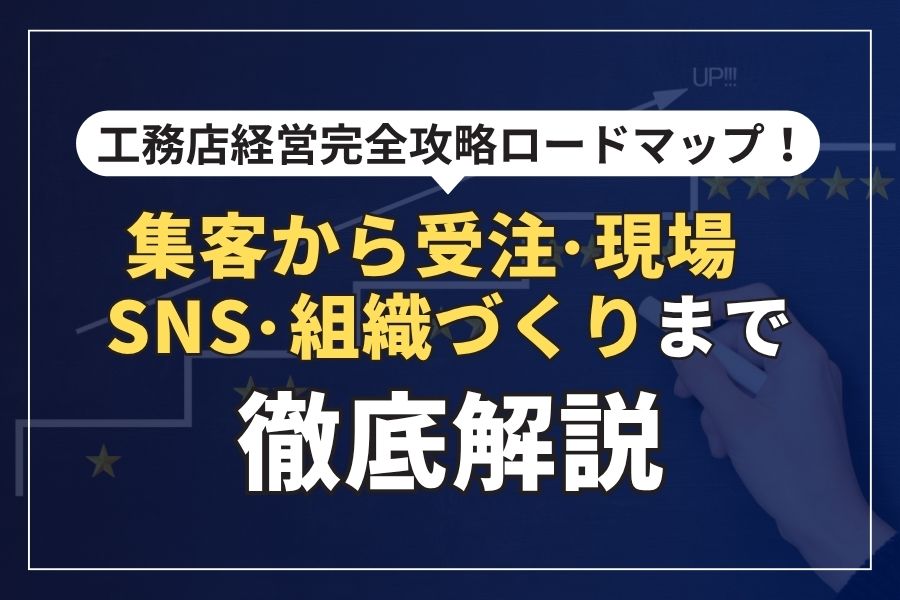
皆さんこんにちは。
ウィズモーの小倉です。
「もっと集客したいのにうまくいかない」「利益が思ったほど残らない」「人が定着せず育たない」
工務店経営をしていると、こんな悩みが尽きないものです。
実は、地域で長く選ばれ続ける会社には共通するポイントがあります。
それは、自社の強みを徹底的に尖らせること、当たり前を継続してブランドに変えること、そしてWEBやSNSを駆使して見込み客を育てる仕組みを持つことです。
この記事では、集客・受注・現場管理・SNS・組織づくりまで、工務店経営を成功に導くロードマップをわかりやすく解説します。
ぜひ最後まで読んで、自社の成長に役立ててください。
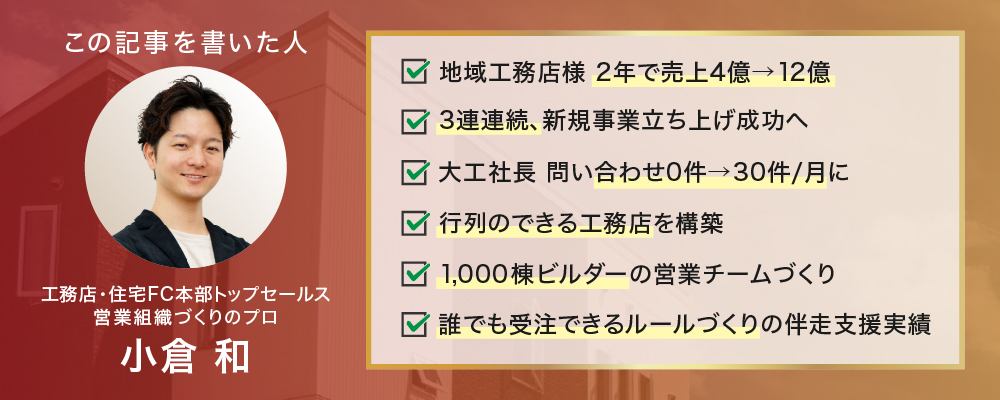
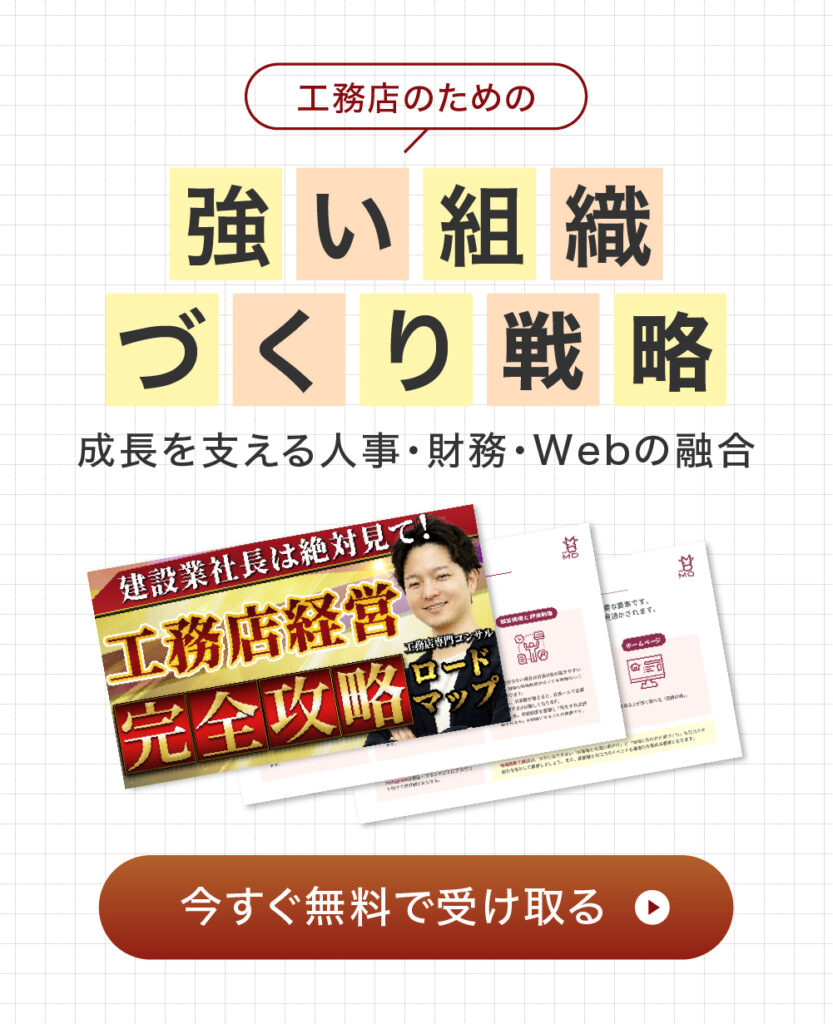
【目次】
・経営を成功に導くために欠かせない考え方
・ホームページとWEB導線が経営を支える要
・集客から受注まで営業プロセスを最適化する
・現場と原価管理で利益を確実に残す
・SNS戦略で地域で選ばれるブランドをつくる
・経営計画と組織づくりで未来を描く
・まとめ
関連動画はこちら ▼
経営を成功に導くために欠かせない考え方
工務店や住宅会社を経営していると、利益が思うように伸びなかったり、人が育たなかったりと悩みは尽きません。
ただ、地域で勝ち残り続ける会社は共通して次の3つを徹底しています。
多くの工務店経営者が抱える課題
住宅業界では、多くの経営者が同じような悩みを抱えています。
人材不足で職人や現場監督が確保できない。
価格競争に巻き込まれ利益が減る。
下請けから抜け出せず、自社ブランドが育たない。
さらに売上が伸びても利益が残らず、結局資金繰りで苦しむケースも多いです。
こうした悩みは珍しいことではなく、全国どこの地域でも同じ構造的な課題です。
自社の強みを明確にして尖らせる
課題を抜け出すためにまず必要なのは、自社の強みをしっかり理解して尖らせることです。
デザインが得意なのか、性能重視なのか、コストパフォーマンスで選ばれるのか。
何でもできますとアピールすると逆に選ばれません。
大事なのは、誰にどんな価値を届けたいのかを明確にし、ターゲットを決めたうえでその層に響く打ち出しをホームページや営業トークに落とし込むことです。
凡事徹底が地域一番店への近道
強みを打ち出したら、それを支えるのは凡事徹底です。
当たり前のことを徹底的にやりきる会社が、結局地域で一番に選ばれるようになります。
現場をきれいに保つ、報連相を早くする、引き渡し後の点検を欠かさない。
こうした小さな積み重ねが紹介や口コミを生み、ブランド力になっていきます。
目立つ広告や価格勝負だけに頼るのではなく、毎日の当たり前を丁寧に続けることが結局一番の経営戦略です。
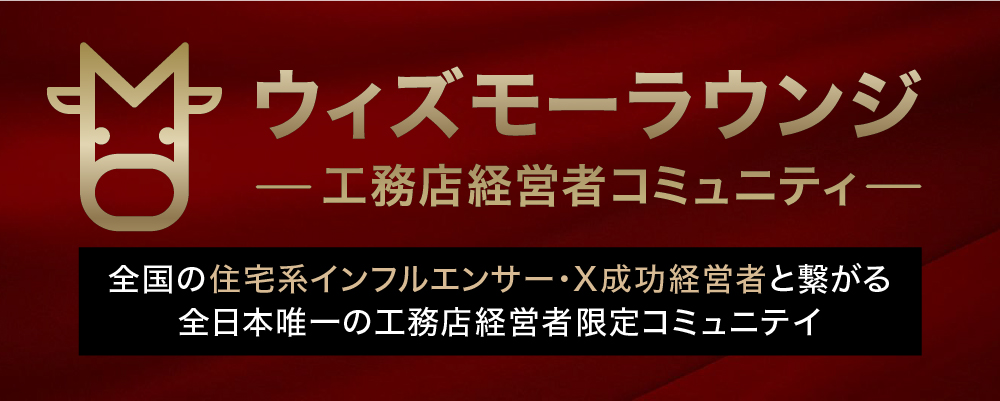
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎
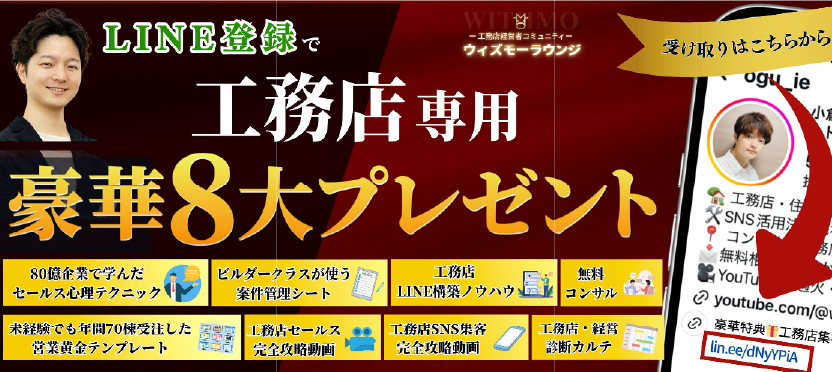
ホームページとWEB導線が経営を支える要
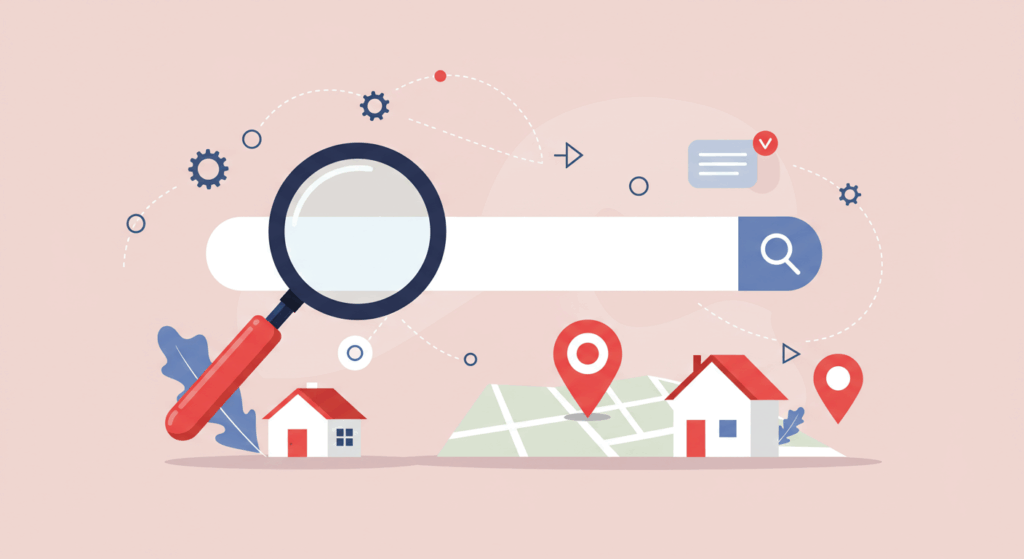
今や家づくりを考え始めた多くの人は、最初にネットで検索し、複数の会社を比較します。
その中で選ばれるかどうかを決めるのは、どれだけ自社の魅力をWEBでしっかり伝えられているかです。
見込み客を引き寄せ、ファンに育て、最後は契約までつなげる。この一連の仕組みを整えることが、これからの工務店経営では欠かせません。
尖ったホームページが見込み客を引き寄せる
多くの工務店や住宅会社のホームページは「高性能」「デザインにこだわり」など同じ言葉が並び、差が見えにくいのが現状です。
見込み客に選んでもらうには、どんな暮らしを誰に届けたいのかを明確にし、それを徹底的に尖らせることが大切です。
例えば「自然素材を使って子どもの健康を守る家」や「30坪で広がりを感じる設計で心地よく暮らす家」のように、誰のどんな課題を解決する家なのかをはっきり打ち出す。
この尖りが、比較検討しているお客様の心に引っかかり、問い合わせへとつながります。
また尖らせるためには「どのターゲットにするか」を決める必要があります。
逆に言うと、あえて捨てる客層を決める勇気が重要です。
すべての人に良く見せようとすると、結局誰にも響かなくなってしまいます。
資料請求や問い合わせにつなげる導線設計
ホームページはただきれいに作ればいいわけではありません。
最終的に問い合わせや資料請求をしてもらうために、どの順番でページを見てもらうかを設計しておく必要があります。
例えばトップページに訪れたお客様はまずビジュアルやキャッチコピーで「この会社は他と違うな」と感じ、次に施工事例やオーナーの声で「信頼できそう」と思うようになります。
そして性能や価格、よくある質問などで疑問を解消し、最後にキャンペーン情報や来場特典を見て「資料請求してみようかな」となる。
この流れを一本道で作るのが理想です。
無計画にページを足すと、訪問者は何をどう見ればいいか分からず離脱します。
必ず「見込み客が最後にどんな行動をとるのか」を逆算して作り込むことが重要です。
リスト獲得後の教育とファン化の仕組み
問い合わせや資料請求をしたお客様は、すぐに契約するわけではありません。
ここからが本当の勝負です。
多くの会社がやりがちなのが、資料を送った後ほとんど何も連絡しないケース。
これではせっかくの見込み客を逃してしまいます。
LINE公式アカウントやステップメールを使って「家づくりの進め方」「資金の考え方」「完成事例紹介」など、自社の魅力や家づくりの知識を少しずつ伝えていくことで、自然とファン化していきます。
問い合わせから10日以内にアポを取ると契約率が大きく上がると言われているので、できればすぐ連絡を取り、次の相談や見学会に誘導することがポイントです。
完成見学会前に価値を提供するイベントの重要性
完成見学会はお客様が最も心を動かす場所ですが、その前にハードルを低くした小さなイベントを用意するのが非常に効果的です。
例えば資金計画セミナーや土地相談会、最近ではインスタライブでの施工事例紹介やOBインタビュー配信も増えています。
こうした「お得な情報が手に入る場」を挟むことで、お客様は安心して次のステップに進めます。
ただ見学会だけを告知しても来場ハードルは高いので、その前に気軽に参加できるコンテンツを作って関係性を築いておくと、最終的に見学会での成約率が格段に上がります。
関連動画はこちら ▼
集客から受注まで営業プロセスを最適化する
どれだけ集客に成功しても、その先の営業が場当たり的だと契約は安定しません。
多くの工務店が抱える課題は、商談の進め方が営業マン任せになり、経験や感覚に頼り切ってしまうことです。
これでは成果が個人の力量に大きく左右され、業績は安定しません。
営業プロセスを最適化するには、まず「自社は何回の商談で契約を決めるのか」をはっきり決めることから始めます。
例えば4回目の打ち合わせで契約を決めると設定すれば、そこまでに資金計画をまとめ、プランやローン審査まで完了しておく必要が見えてきます。
この目標に沿って、1回目は何を話し、2回目はどんな提案をするかを具体的に決め、各ステップにKPIを設定します。
ただ流れを決めるだけでは不十分です。
重要なのは、その流れを誰でも再現できるようにすること。
初回商談では何をゴールにするか、そのためにどの資料を使い、どんな話をするのかをマニュアル化し、それをロープレで練習します。
さらに見本動画を作っておけば、新人も繰り返し学べるので、経験が浅くても一定水準の提案ができるようになります。
最後に欠かせないのがフィードバックです。
営業の進捗確認をするときに、上司が細かく指示を出しすぎると営業マンは思考停止し、自ら改善できなくなります。
案件の状況や課題、次にどう動くかを自分で話させ、そのうえで必要なら選択肢を一緒に考える。
これを繰り返すことで営業マンが自分で考える力を持ち、結果として組織全体の営業力が底上げされます。
こうした仕組みを整えることで、誰でも同じ流れで営業ができ、安定して受注できる組織をつくることが可能になります。
現場と原価管理で利益を確実に残す
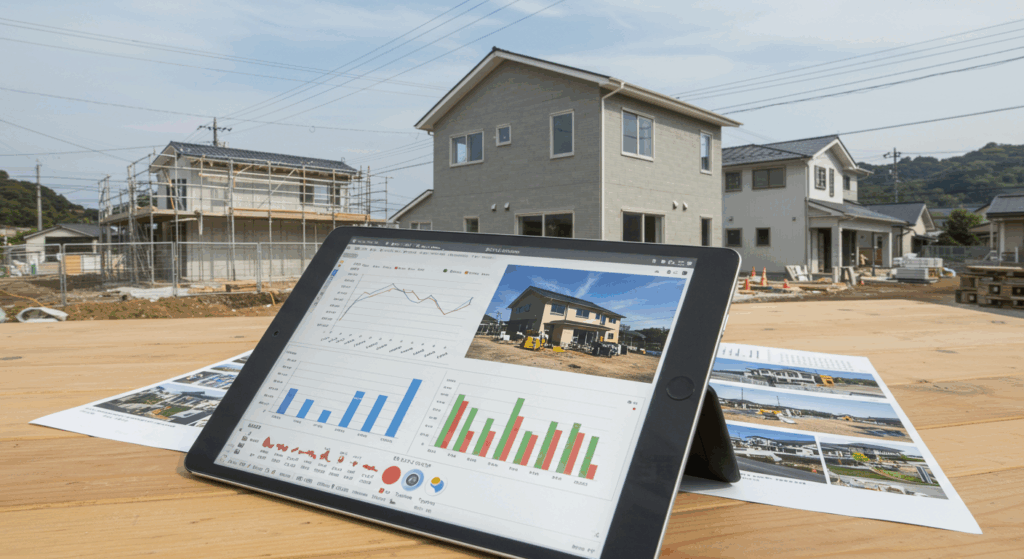
どれだけ集客や営業を頑張って契約が取れても、最終的に利益が残らなければ経営は苦しくなります。
工務店経営で最も多い悩みは「気づけば利益が減っていた」という状態です。
こうならないためには現場の品質と原価管理を徹底し、紹介が出やすいタイミングを逃さないことが大切です。
誰が担当しても同じ品質を保つ仕組みをつくる
いい家をつくるのは当たり前ですが、担当する現場監督や職人によって品質にムラが出てしまう会社も少なくありません。
これを避けるためには、家づくりの基準や収まり方を全社で統一し、誰がやっても同じ水準で完成できる仕組みを作ることが大事です。
たとえば有名チェーンの飲食店では、誰が盛り付けても同じ商品が出せるようマニュアルが細かく決まっています。
住宅でも基準を設け、工事中の写真管理やチェック項目を徹底すれば、属人化を防げます。
結果的にクレームや手直しが減り、利益率を守ることにもつながります。
工程管理ツールを活用して利益率を維持する
住宅業界では原価が最後にズルズル増えて利益が削られるケースが多いです。
契約時には粗利30パーセントを確保していたはずが、引き渡すと25パーセントに下がっている、そんな話は珍しくありません。
原因は工程の遅延や追加工事の管理不足です。
現場で何が起きているかリアルタイムで把握できるツールを使い、工程通りに進んでいるか、予定外のコストが発生していないかを逐一チェックすることが重要です。
最近はアンドパッドやランドリーワークスのようなツールが普及しており、写真や日報をすぐ共有できるため、現場監督が複数抱えていても見逃しを減らせます。
紹介が最も生まれやすい引き渡し当日を活かす
紹介で受注が取れれば広告費をかけずに契約が増え、利益率も自然に良くなります。
その中でも一番紹介が生まれやすいのは引き渡し当日です。
人は感動が一番高まった瞬間に、誰かにその体験を話したくなるものです。
お客様にアンケートをお願いし、家づくりの満足度や紹介したい人がいないかをそっと尋ねてみましょう。
この一言が紹介を生むきっかけになります。
半年後や一年後では感動は薄れてしまいます。
引き渡し当日の熱量を最大限活かすことが、紹介獲得を増やすポイントです。
SNS戦略で地域で選ばれるブランドをつくる
今の時代、家づくりを考える多くの人がまずネットで情報を集めます。
そのためホームページだけでなくSNSの活用が欠かせません。
SNSは単に発信ツールではなく、集客・採用・ブランディングすべてに影響する重要な経営資源です。
YouTubeは集客・採用・業者用の三本立てが理想
YouTubeをうまく使うと、自社の強みや家づくりへのこだわりを圧倒的に伝えられます。
ただ1つのチャンネルで全部やろうとすると内容が散らばって伝わりにくくなるので、役割ごとにチャンネルを分けるのが効果的です。
・集客用はルームツアーやオーナーインタビュー、家づくりセミナーを発信し「自分もこの会社に頼みたい」と思わせる内容を届けます。
・採用や社内教育用は、社員の声や社内イベントの様子を見せることで「楽しそうな会社」「ここで働きたい」と感じる人材を惹きつけます。
・業者用は施工マニュアル動画で現場品質を守るためのものです。図面や仕様書だけでは伝わりにくい細かい部分を動画に残しておくと、いつ誰が見ても同じ基準で仕事ができます。
結果的に業者教育の負担が減り、現場トラブルややり直しが減少します。
Xは社長自ら情報発信して採用とブランディングに使う
X(旧Twitter)は社長自らが発信するのが一番効果的です。
地域の経営者や職人、異業種のフリーランスがよく見ており、ビジネス的なつながりを持つのにぴったりです。
社長がどんな考えで会社を経営しているか、どんな暮らしを地域に届けたいのかを日々の投稿で伝えると、共感や信用が自然と積み上がります。
それは結果的に採用や業者ネットワークを広げることにもつながります。
「この社長の元で働きたい」「一緒に仕事をしたい」と感じてもらえたら、採用広告を打つよりずっと質の高い出会いが生まれます。
Xは短文でのコミュニケーションが主なので、継続して投稿を続けやすいのもメリットです。
Instagramは商品やブランドごとにアカウントを分ける
Instagramは家づくりのイメージを写真と動画で直感的に伝えるのに最適です。
ただし複数のコンセプトを1つのアカウントで投稿すると、見込み客に「結局どんな暮らしを提案する会社なのか」が伝わりにくくなります。
例えば、別荘風のラグジュアリーな家を打ち出したいのに、同じアカウントにかわいらしい北欧風の平屋を混ぜてしまうとブランドがぼやけます。
世界観を尖らせるためには、商品ごと・ブランドごとにアカウントを分けることがポイントです。
平屋なら平屋専用、狭小住宅なら狭小住宅専用、と決めることでファンがつきやすくなり、その暮らしに共感した人が集まります。
これは結果として見込み客の質も高まり、受注につながる確率をぐっと上げます。
SNS運用も結局は「誰に」「どんな暮らしを届けたいか」を尖らせ、それをブレずにやり続けることが重要です。
どんなに見た目のきれいな投稿をしても、方向性がバラバラだったり続かなければブランドにはなりません。
当たり前のことを徹底して積み重ねる、それが地域で選ばれる会社になる一番の近道です。
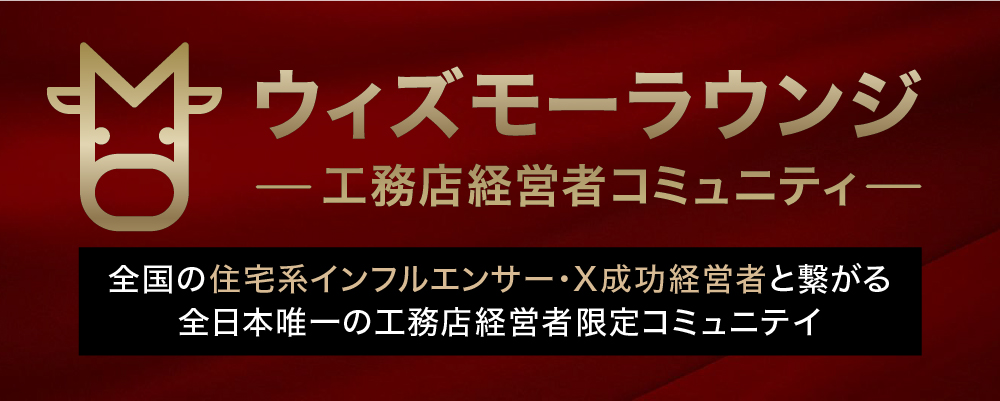
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎
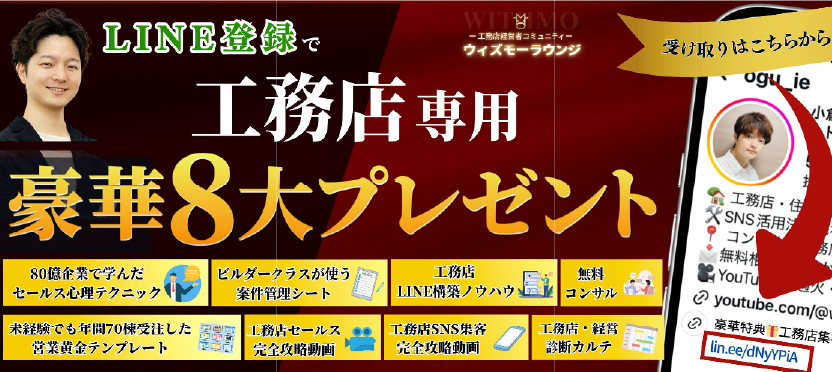
経営計画と組織づくりで未来を描く

多くの工務店経営者が抱える悩みは、売上を追うばかりで「どこに向かう会社なのか」がはっきりせず、採用や育成が場当たりになりやすいところです。
結果として、せっかく人を採用しても早期離職が続いたり、利益が思うように残らない会社は少なくありません。
ここから抜け出すには、まず会社の未来を描くことが必要です。
ビジョンと会社ルールが採用や育成の基盤になる
どんな地域に、どんな価値を提供したい会社なのか。
これを明確にしないまま採用すると、そもそも合わない人を採用してしまったり、入社後に「思っていた会社と違った」と言われてしまう原因になります。
例えば「健康を軸にした暮らしを叶える工務店」なら、スタッフ自身も健康に気を遣い、残業を減らす、ジャンクフードを禁止するなどルールを作っても良いでしょう。
こうしたルールをビジョンと一緒に掲げると、自然に社風に合う人材が集まり、採用後の教育もブレにくくなります。
利益から逆算して立てる現実的な経営計画
経営計画というと、多くの経営者がまず売上目標を掲げますが、本当は逆です。
最初に「どのくらい利益を残したいのか」を決め、そこから原価、販管費、人件費を引き、必要な粗利や売上を逆算するべきです。
たとえ売上が10億円あっても、利益が残らなければ意味がありません。
3年後5年後にどの水準まで会社を持っていくのかを決めると、そこに向けて毎月いくつ受注を取ればいいのか、人はどれだけ必要なのかが自然に見えてきます。
人事評価制度で社員のやる気と定着率を高める
採用できても人が育たず、すぐに辞められてしまう会社は少なくありません。
よく聞くのが「社長の気分や主観で評価が決まるので頑張りどころが分からない」という声です。
評価制度を整え、どんな行動や成果を出したら給与が上がるのか、どんな研修を受けたら次のステージに進めるのかを見える化すると、社員は安心して挑戦できます。
昇給・昇格の道筋がはっきりすることで、やる気や定着率も高まり、結果として会社全体が安定して成長していきます。
関連動画はこちら ▼
まとめ
工務店経営を成功させるには、まず「誰にどんな暮らしを届けたいのか」を明確にし、自社の強みを尖らせることが重要です。
次に、現場をきれいに保ち報連相を徹底するなど、当たり前のことを継続して実行しブランド力を高めます。
また、ホームページやSNSを活用して見込み客を引き寄せ、資料請求後の教育でファン化を図る仕組みも欠かせません。
さらに、人事評価制度や経営計画を整え、社員が安心して成長できる環境をつくることで、安定的に利益を残せる組織へと導けます。
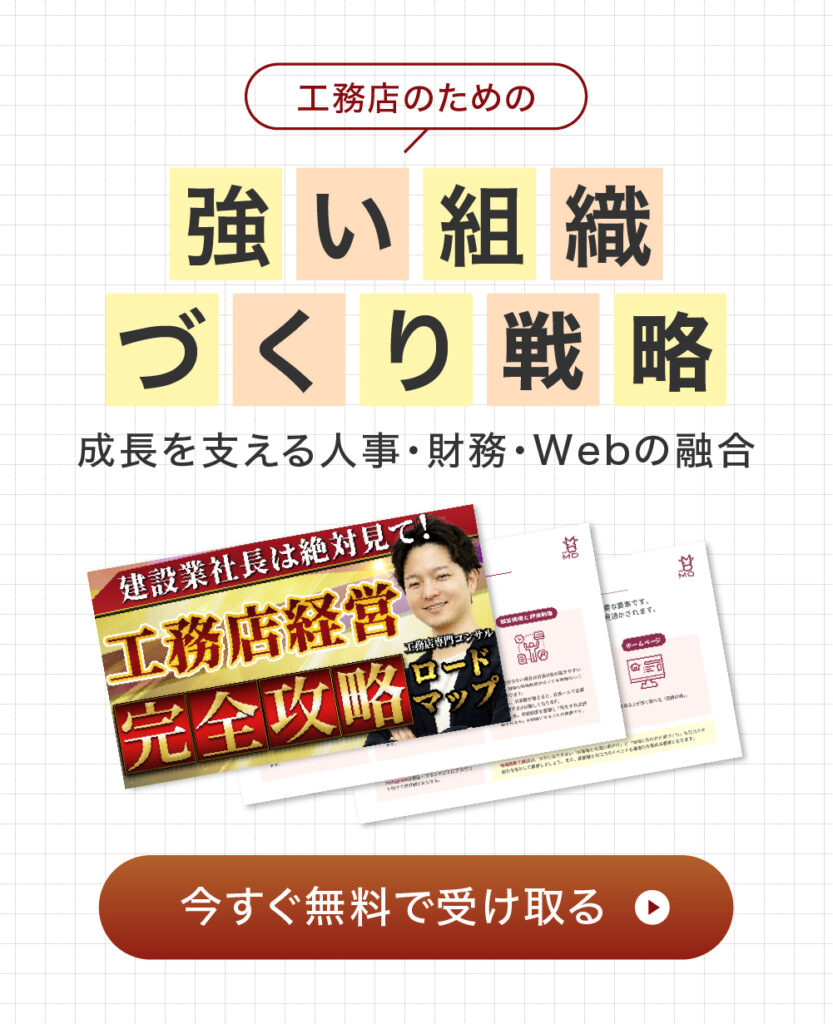
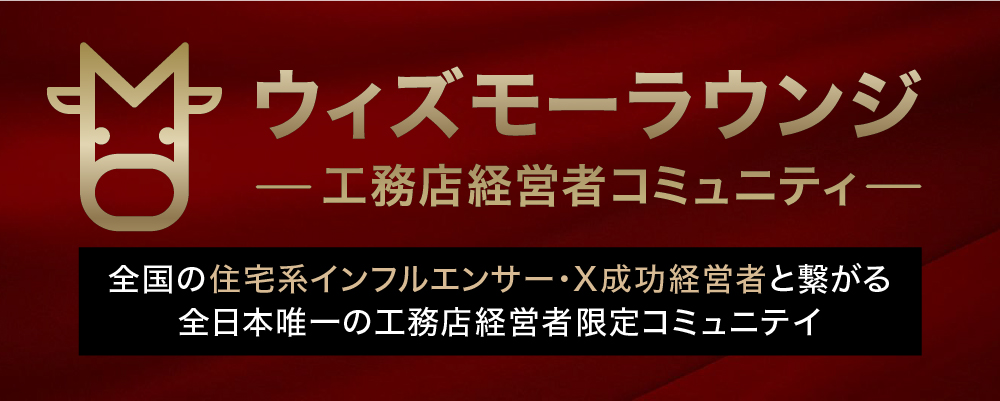
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎