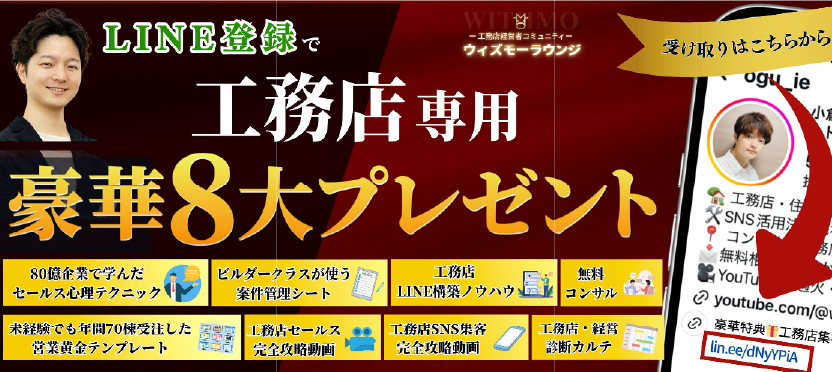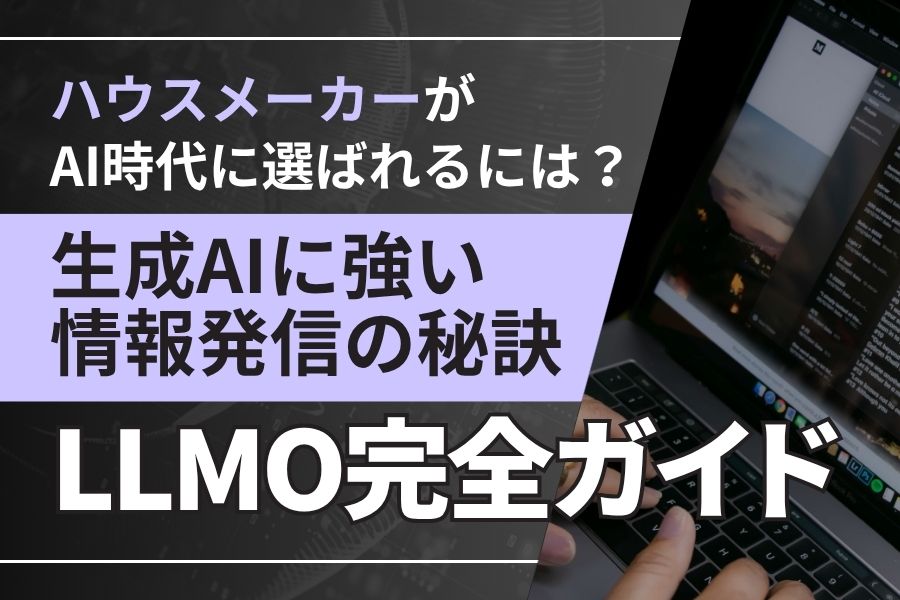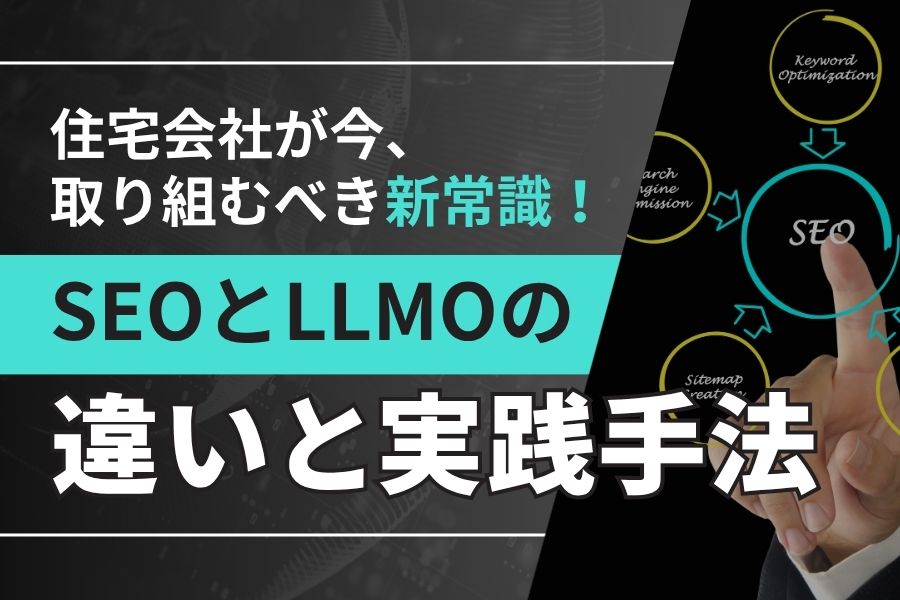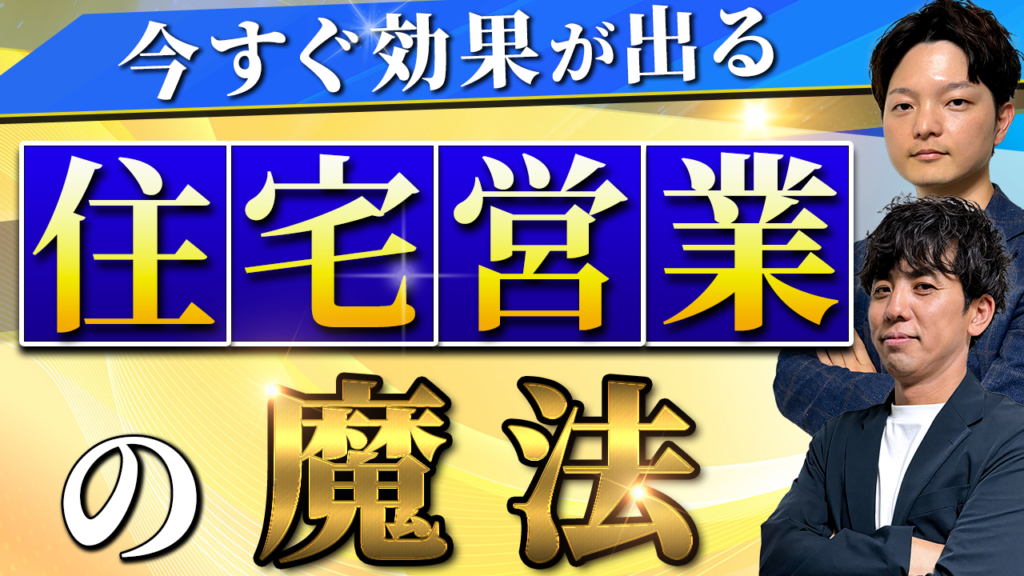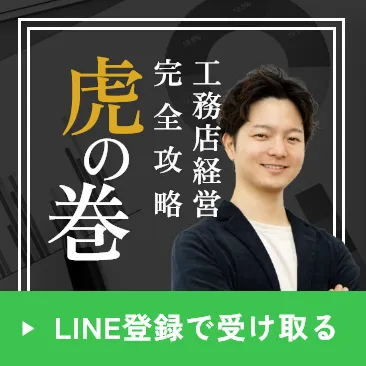工務店経営を黒字倒産から守る財務戦略完全ガイド
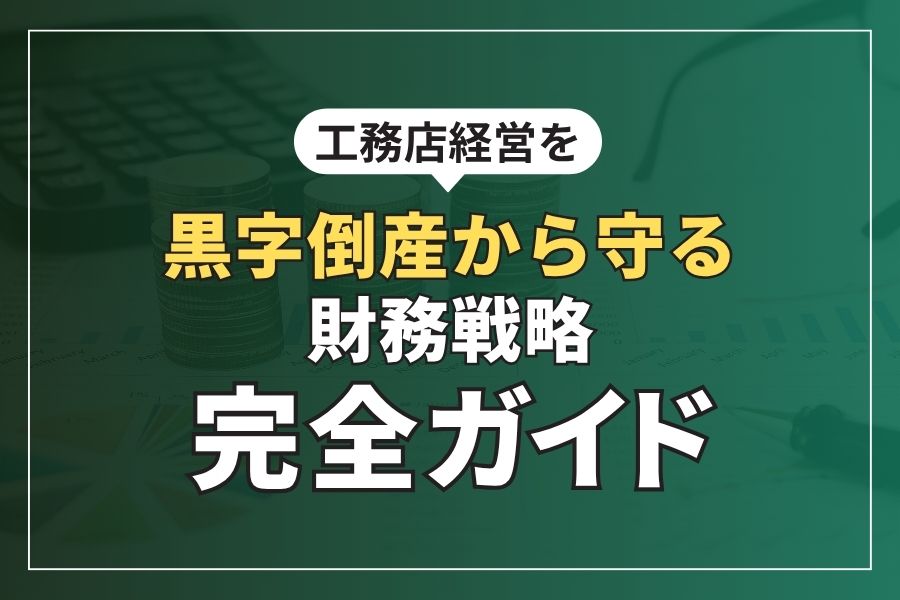
皆さんこんにちは。
ウィズモーの小倉です。
工務店経営をしていて「黒字なのにお金が足りない」「税金で資金が急減した」そんな経験はありませんか?
住宅業界は売上が大きくても資金繰りが非常に難しく、黒字倒産が多発する業界です。
今回は資金ショートを防ぎ、安心して受注を増やせる工務店になるための財務戦略を徹底解説します。
資金繰り表の作り方から税金対策、銀行との関係づくりまで詳しくまとめましたので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
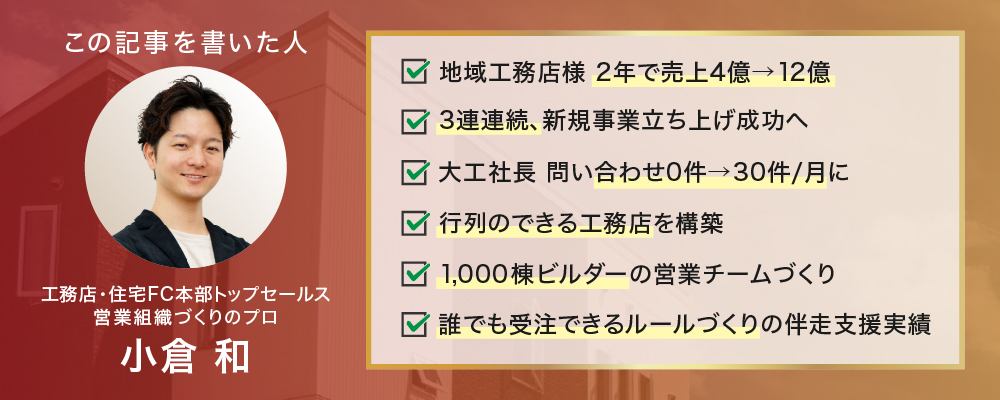

【目次】
・まず知ってほしい工務店の財務リスク
・工務店経営の財務を考えるうえで必須の視点
・なぜ黒字なのに資金ショートが起きるのか
・倒産しない工務店になるための資金繰り対策
・利益率の低い業界で確実に利益を残すには
・3年後の口座残高を把握するキャッシュフロー経営
・財務が強い工務店は何をしているのか
・成功事例から学ぶ利益体質のつくり方
・まとめ
関連動画はこちら ▼
まず知ってほしい工務店の財務リスク
多くの公務店経営者が日々感じている悩みの一つに、思ったよりお金が残らないという問題があります。
売上は立っているのに、ふたを開けると手元資金が厳しくなっている。
この原因の多くは、建設業特有のキャッシュフローのタイムラグにあります。
住宅の仕事は契約から完成引き渡しまで半年ほどかかるのが一般的です。
その間に職人や業者への支払いや広告費、諸経費などの出金がどんどん発生しますが、入金は工事の節目や完成後。
つまりお金が入るより先に大きな支払いが続く構造です。
この状態をきちんと把握できず、単純にPL(損益計算書)だけを見て安心してしまう経営者は少なくありません。
利益が出ているように見えても、資金繰り表を見れば赤字、ということは珍しくありません。これが「黒字倒産」の正体です。
実際に、決算書では黒字なのに口座残高が足りず倒産してしまう会社は業界に非常に多くあります。
売上が上がれば上がるほど先出しの経費も大きくなり、資金不足のリスクはむしろ高まります。
さらに税金や予定納税の支払い時期を軽視しがちな会社も多く、法人税の本税を納めた後、数ヶ月後に前期を基準にした予定納税がやってくることで資金が一気にショートするケースもよくあります。
だからこそ資金繰りを「ざっくり」ではなく「数ヶ月先、数年先まで細かく」把握しておくことが重要です。
どの月にどれだけ入金があり、どれだけの支払いが控えているのかを具体的に計画し、将来の資金不足をあらかじめ銀行と共有して対策しておく。
これが経営を守る大きなポイントです。
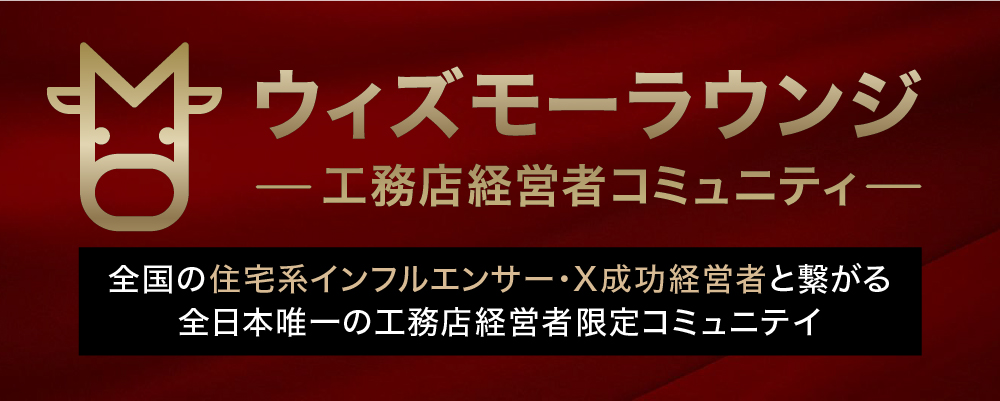
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎
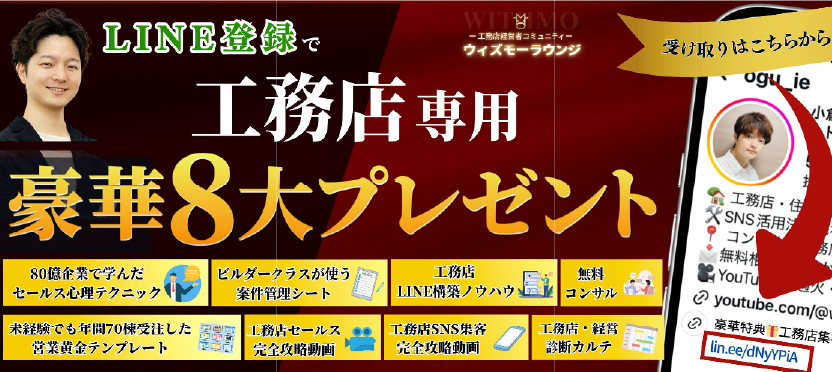
工務店経営の財務を考えるうえで必須の視点

住宅やリフォームの仕事をしている工務店は、売上規模が大きくなる一方で、実は資金繰りに失敗しやすい業種です。
ここでは多くの会社が陥りがちな財務の落とし穴と、それを防ぐために必須の考え方をまとめました。
PL(損益計算書)だけを見ても資金の実態は分からない
多くの工務店経営者は、毎月税理士さんから送られてくる損益計算書(PL)を確認して、黒字だから大丈夫だと思い込みがちです。
しかしPLは売上や利益を示すものにすぎません。実際に会社の口座にいくらお金が残っているのか、どれだけ将来支払いが控えているのかは反映されていません。
例えば工務店の場合、引き渡しの半年以上前から材料を発注し、職人へ支払いが発生します。けれど入金は着工金、中間金、最終金と分割で入り、利益として計上された売上が実際に全額振り込まれるのは何ヶ月も先です。
PLだけを見て安心し「まだ大丈夫」と資金を使い過ぎると、半年後の大きな支払いで資金が足りずに慌てるということになりかねません。
9割の工務店が資金繰り表を作らないリスク
資金繰り表とは、いつ、どれくらいの入金があり、どのタイミングでどれだけの支払いがあるのかを見える化した表のことです。
これを持っていない工務店は非常に多く、財務のプロがこれまで見てきた約500〜800社の中で9割以上が資金繰り表を作っていませんでした。
資金繰り表がないと、
・税金の支払いタイミングで資金不足に気付く
・予定納税が来たのにお金が足りない
・新しい案件を受注したくても支払いに充てる現金がなくて受けられない
など、経営の大きな制約になります。
これを避けるためには、せめて月単位で資金繰り表を作り、会社の財布を可視化する必要があります。
将来の資金ショートを未然に防ぐには
資金繰り表を作れば、1ヶ月後、半年後、1年後の資金残高がどうなるかが分かるようになります。
例えば来年の決算後に予定納税で多額の税金が発生すると分かっていれば、早めに銀行へ融資相談をして資金を確保できます。
銀行も、毎月キャッシュフローをきちんと把握し、いついくら必要かが明確な会社には積極的にお金を貸してくれます。
その場しのぎではなく、将来の資金不足を予測し、前もって手を打てる会社は強いです。結果として売上を伸ばすチャンスが来ても、安心して受注でき、利益を残し続けることができます。
関連動画はこちら ▼
なぜ黒字なのに資金ショートが起きるのか
工務店経営では、決算書の損益計算書(PL)で黒字なのに、実際には資金が足りずに頭を抱えるケースが少なくありません。
これがいわゆる黒字倒産です。こうした資金ショートは、建設業ならではのキャッシュフローの構造を正しく理解していないと防げません。
建設業特有のキャッシュフロー構造
工務店の仕事は、契約から入居までに長い時間がかかるビジネスです。
住宅1棟を建てるのに半年から1年という時間が必要になることも珍しくありません。
通常、請負契約を結ぶと「着工金」「中間金」「竣工金」のように数回に分けて入金されますが、その多くは工事が進んでからの支払いです。
例えば3,000万円の住宅を受注しても、着工時に入るお金は全体の30%程度。
その後に資材調達や職人への支払いなどを進め、完成する頃にはようやく全体の入金が終わります。
この構造上、契約が増えれば増えるほど、工事前半はお金が出ていくばかりで、口座残高はどんどん減っていきます。
だからこそ売上が上がった時こそ「いつキャッシュが入ってくるか」を把握しないと、大きな落とし穴にはまってしまうのです。
先払いの経費が資金を圧迫する
もうひとつ工務店経営で忘れがちなのが、材料費や下請け業者への支払いは先に発生するという点です。
木材やサッシ、クロスといった住宅資材は一度に数百万円単位で発注することも多く、先払いが一般的です。さらに職人への手間賃も現場が進むごとに支払われます。
ここで怖いのは複数現場を同時に抱えている場合です。
例えば3件同時進行していれば、その分の資材仕入れや職人への支払いが一気に重なり、一時的に数千万円規模の資金が出ていくこともあります。
PL上はしっかり利益が出ていても、手元の現金が底をつけば、その時点で支払い不能、つまり倒産という最悪のシナリオになってしまうのです。
税金のタイムラグが資金ショートの原因になる
さらに忘れてはいけないのが法人税・消費税などの税金です。
決算で利益が出れば、2か月後に法人税・消費税をまとめて支払うことになります。
しかも、税金はそれで終わりではありません。
半年後には「予定納税」として、前期に支払った税金のおよそ半分を前払いする仕組みが待っています。
例えば前年に2,000万円の税金を払った会社は、次の年に予定納税で1,000万円を先に支払う必要があります。
これを知らずに決算後の資金を通常の運転資金に使ってしまうと、半年後に税理士から「予定納税で1,000万円必要です」と言われて青ざめることになるのです。
資金繰り表で未来を把握しておくことが最大のリスクヘッジ
こうしたリスクを防ぐためには、単にPLや決算書を見て黒字だから大丈夫と安心するのではなく、資金繰り表を用意し、いつどこでいくらお金が出ていき、どのタイミングで入ってくるのかをしっかり把握することが不可欠です。
数か月後、半年後の口座残高を常に予測しておけば、資金ショートするタイミングが事前にわかり、早めに融資を準備したり、支払い計画を見直すことができます。
倒産しない工務店になるための資金繰り対策

経営を長く続けるために絶対に欠かせないのが、数字の管理と将来の見通しです。
特に工務店や住宅会社は案件ごとの金額も大きく、資金の出入りが激しい業界です。
利益がしっかり出ているつもりでも、入金が遅れればあっという間に資金が尽きてしまうリスクがあります。
理想は資金繰り表を日繰りで作ることです。
給料日や材料代、業者への支払いだけでなく、税金やクレジットカードの引き落とし日も一目で分かる状態にしておきます。
これを怠ると、知らぬ間に手元資金が減り、必要な時に払えず信頼を失うことになります。
加えて、損益計算書(PL)で今月黒字だからといって安心してはいけません。
月次PLをベースに、税金や予定納税、次の工事の先払い経費など未来に発生する支出をすべて織り込んだ資金繰り表を作ることで、
3か月後や半年後にどれだけ口座に現金が残っているかが具体的に見えてきます。
黒字倒産を防ぐためにはこの「未来のお金の動き」が見えているかが何より大切です。
そして忘れてはいけないのが銀行との関係づくりです。
資金が苦しいタイミングでいきなり借りに行っても、銀行側は警戒し融資を渋るものです。
だからこそ日ごろから数字や計画を共有し、担当者に「この会社なら融資しても安心」と思ってもらえる信頼関係を築いておくことが必要です。
将来の資金ショートを防ぎ、会社を守るのは社長であるあなたのこの小さな積み重ねです。
利益率の低い業界で確実に利益を残すには
建設業は他の業界に比べてもともと利益率が低く、経営の数字管理を少し怠るだけで黒字が吹き飛ぶ厳しい業界です。
だからこそ、数字に強い経営が求められます。
建設業の平均利益率は約3〜5%
上場している大手の住宅会社でさえ営業利益率は5%前後と言われます。
飲食業や美容院でも10%ほど、コンサルティング業界に至っては30%〜50%という高水準です。建設業は構造的に粗利が低く、同じ売上でも残る利益はごくわずか。
経費の使い方を一歩間違えると簡単に赤字になってしまいます。
利益率を守るために経費の目安を持つ
建設業で確実に利益を残すには、売上に対しての各費用の比率をしっかり管理することが大切です。
例えば減価は70%程度までに抑え、粗利を30%は確保すること。
広告宣伝費は売上の3%、人件費は10%以内を目指すのが一つの目安です。
これを超えるとどこかで資金繰りにひずみが出ます。
ダッシュボードでリアルタイムに数字を追う
毎月の数字を紙の決算書やExcelだけで見るのではなく、リアルタイムで数字を追えるダッシュボードを導入する会社が増えています。
例えば今どれだけ案件が動いていて、広告費は何パーセント、粗利率はどうか、人件費率はどうか。これを月単位でなく日単位や週単位で管理する会社ほど、数字のズレに早く気づき、対策を打てます。
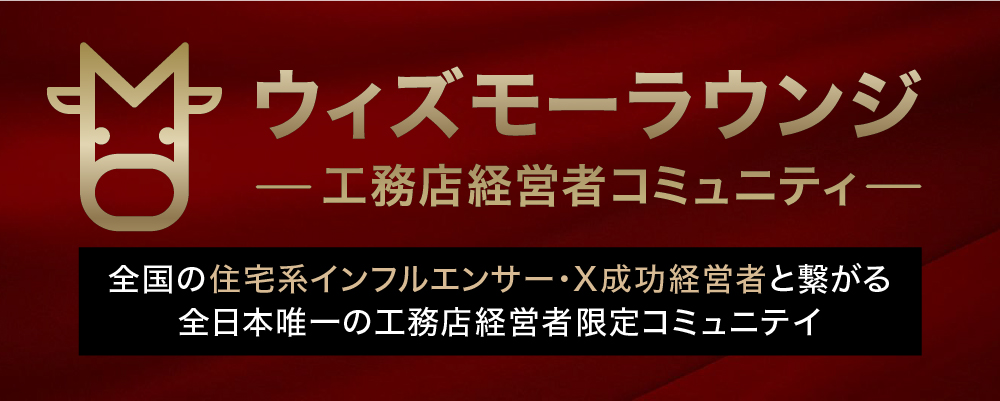
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎
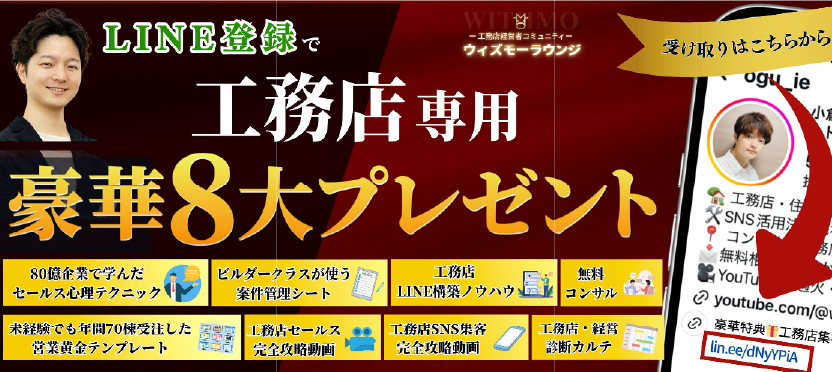
3年後の口座残高を把握するキャッシュフロー経営
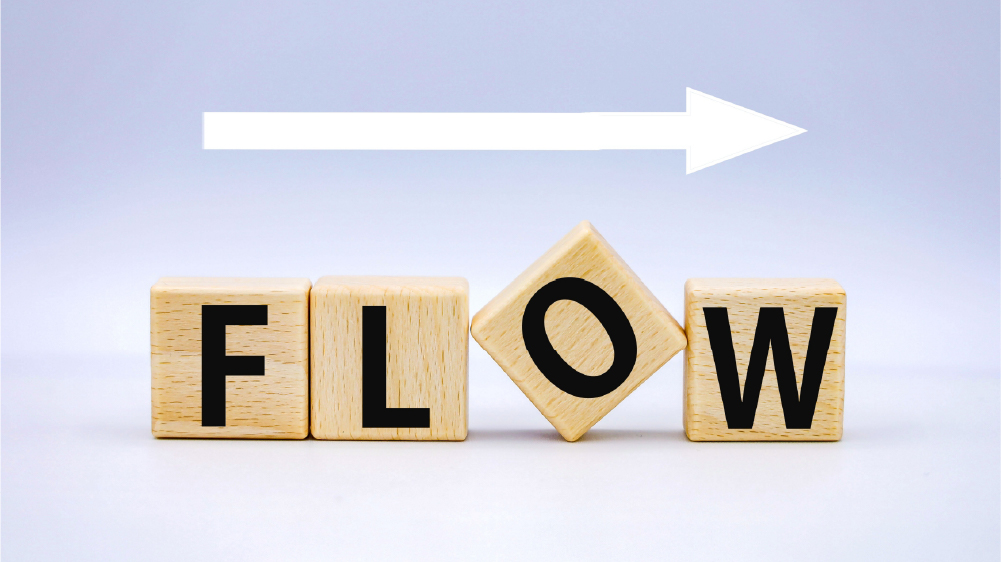
公務店経営では目先の売上やPL上の利益に一喜一憂しがちですが、本当に重要なのは数年後の資金残高です。
これを把握することで黒字倒産を防ぎ、事業を安心して拡大できます。
売上の入金タイミングを計画に落とし込む
建設業では、契約したからといってすぐにお金が入るわけではありません。
着工金、中間金、完工金といった段階的な入金が一般的で、実際に全額が入るまでに半年から1年かかるケースも多いです。
このタイムラグを無視して売上だけを追っていると、手元資金が足りなくなる危険があります。
だからこそ、資金計画には必ず「いつ請求が立つか」ではなく「いつ実際に入金されるのか」を正確に記入することが必要です。
例えば売上計画表の横に、入金予定月を並べて管理するだけでも、資金繰りの精度は格段に上がります。
税金や予定納税を織り込んだ資金計画を立てる
もう一つの落とし穴が税金です。決算後2ヶ月以内には法人税・消費税の支払いがあり、さらに黒字が続けば半年後には予定納税があります。
決算が終わったから一息つける、と思っていると、突然数百万円単位の資金が必要になり慌てることに。
資金繰り計画を作る際は必ず税金支払月を見込んでおきましょう。
決算時に納税額をシミュレーションしておき、法人税や予定納税が発生する月に必要額を計上しておくだけで、資金ショートを未然に防げます。
銀行融資を受ける最適タイミングを把握する
先々の資金残高を見える化しておくと、いつ融資を受ければ良いかがはっきり分かるようになります。
資金が不足してから動くのではなく、将来の資金が底をつく少し前に銀行に相談し、準備を整えることが肝心です。
資金計画を月単位で細かく作り込んでおけば、銀行側も「この会社は数字をしっかり把握している」と評価してくれ、融資の審査もスムーズに進みます。
逆に言えば、資金繰り表を持たずに「お金が足りなくなりそうなので貸してほしい」と駆け込むのは最も避けたいパターンです。
財務が強い工務店は何をしているのか
経営を続ける上で、もっとも恐ろしいのは突然の資金ショートです。
黒字決算なのに手元資金が尽きてしまう黒字倒産は、どの工務店にも起こり得る問題です。
財務が強い会社は、それを防ぐために普段から徹底して仕組みを作っています。
ここでは、そのポイントを3つに分けて紹介します。
資金繰りを数値化して未来の危機を回避する
財務に強い工務店は、資金繰り表を必ず作り込んでいます。
受注から着工、中間金、完工金といった入金タイミングを具体的に並べ、出金予定も月単位で詳細にリストアップ。
こうしてキャッシュフローを視覚化することで、半年後や1年後に資金がどのように動くかが一目で分かるようになります。
これにより資金が底をつく前に対策を打てるため、倒産リスクを限りなく低くできます。
経費配分を守り続ける仕組みを持つ
建設業は利益率がもともと低いため、経費のコントロールは死活問題です。
財務がしっかりした工務店は、売上に対する広告宣伝費は3%、人件費は10%、減価は70%以内などの経費目安を設け、それを毎期必ず守る仕組みを導入しています。
ダッシュボードや定期会議で進捗を確認し、目標比率を超えないよう日常的に調整しているため、小さなズレが大きな赤字に変わるのを防げます。
経営者自身が財務を理解し、数字に強くなる
最終的に財務を守れるかどうかは、社長自身が数字をどれだけ理解しているかにかかっています。資金繰りや決算書は税理士任せではなく、経営者が自分で中身を把握し、どこに課題があるのかを冷静に判断できる会社は強いです。
銀行との融資交渉でも、数字を根拠に語れる経営者は信頼されやすく、いざというときの資金調達もうまくいきます。
成功事例から学ぶ利益体質のつくり方
目先の売上に追われがちな工務店経営ですが、実際に利益をしっかり残し続けている会社には共通点があります。
そこには計画的に広告費を投じて売上を伸ばし、徹底した工程管理で粗利を守り、数字を武器に資金調達まで有利に進める仕組みがあります。
例えばある工務店は、年間売上の3%を必ず広告費として確保しました。
忙しくなるとつい広告費を減らしがちですが、ホームページやSNS運用、イベントへの投資を止めずに継続した結果、月10件以上の安定した問い合わせを獲得。
コロナ禍で他社が反響減少に悩む中でも前年を超える売上を記録しました。
広告を単なる経費ではなく将来の売上を生む投資と捉え、継続したことが功を奏した形です。
さらに粗利を守るために現場管理を徹底した会社もあります。
どの監督が担当して
も同じ水準の品質が維持できるよう材料手配から施工チェックまでを細かくマニュアル化。
毎月の粗利率をチェックし、少しでも予定を下回る兆しがあれば即座に原因を洗い出し対処する体制を整えました。
その結果、工務店業界で平均と言われる営業利益3%を超え、5%超の利益を安定的に確保しています。
また財務面では、いつ資金が入りどのタイミングで税金や予定納税が出ていくのかを細かく計画。
3年先までの資金繰りを具体的な数字で見える化し、銀行へ示して必要な資金を前もって調達しました。こうした財務計画があることで金融機関からの信頼も厚く、成長フェーズでの資金不足を避けることができています。
こうした取り組みは特別なことではなく、どれも経営を成功に導くために欠かせない考え方です。
これらを一つひとつ実行に移せるかが、長く利益を出し続けられる会社とそうでない会社を分ける大きなポイントになります。
関連動画はこちら ▼
まとめ
工務店経営は売上規模が大きい反面、資金繰りのタイムラグが大きく、黒字倒産が非常に多い業界です。
住宅は契約から入金まで半年〜1年かかるのが一般的で、その間に材料費や職人への支払いが先行し資金を圧迫します。
多くの経営者がPL(損益計算書)だけを見て黒字だから安心と誤解しますが、実際の資金残高や将来の支払いを把握できるのは資金繰り表だけです。
これを作ることで半年後や1年後の資金ショートを事前に予測し、銀行融資を早めに準備できます。
また税金や予定納税のタイミングを見込むことも必須です。
普段から数字を見える化し、銀行と計画を共有して信頼を築いておくことで、安心して受注を増やし安定した経営が可能になります。

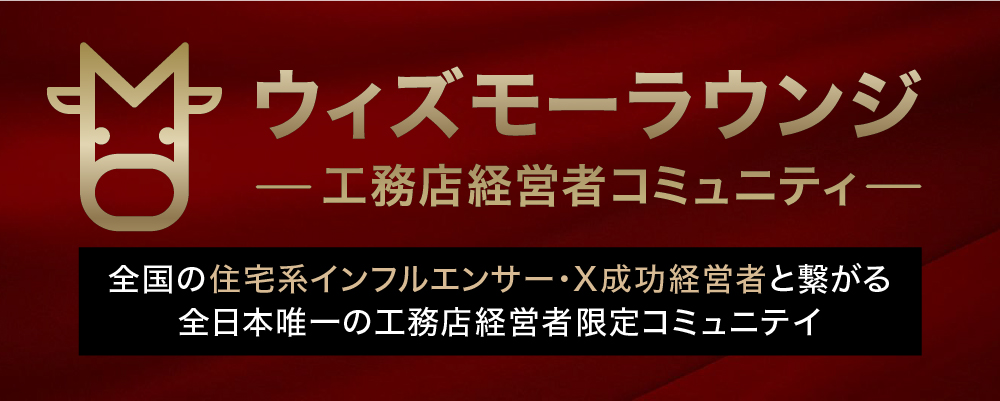
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎