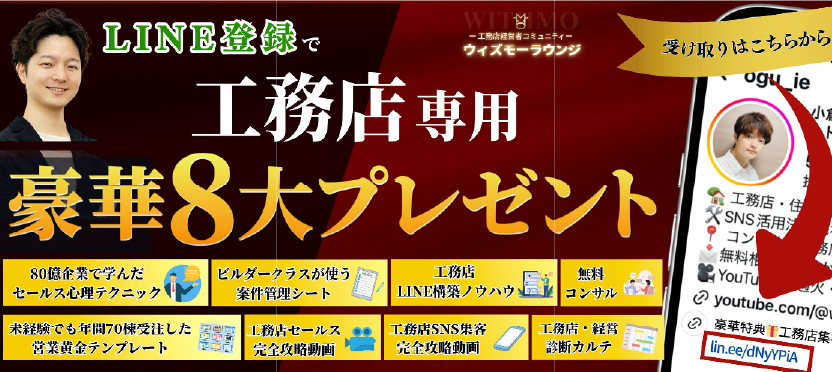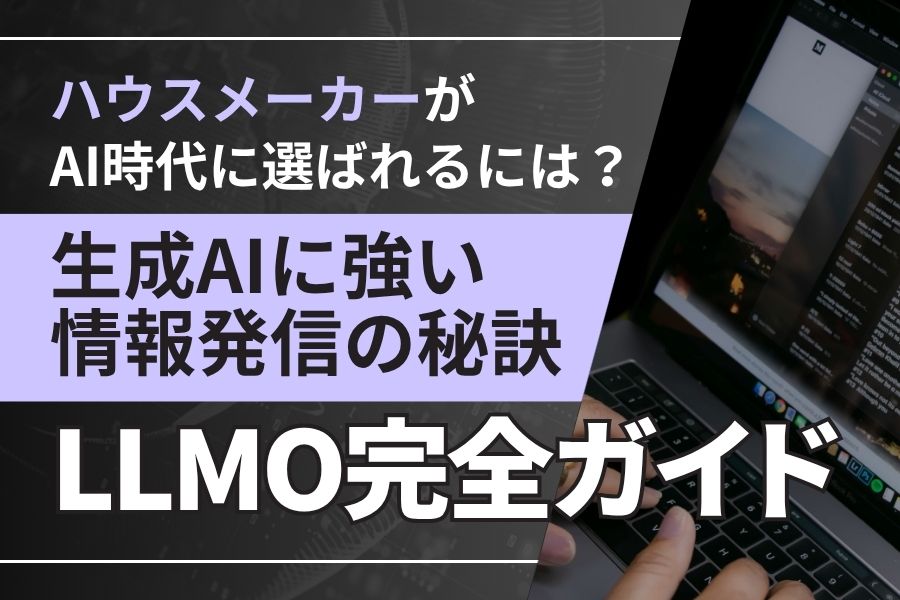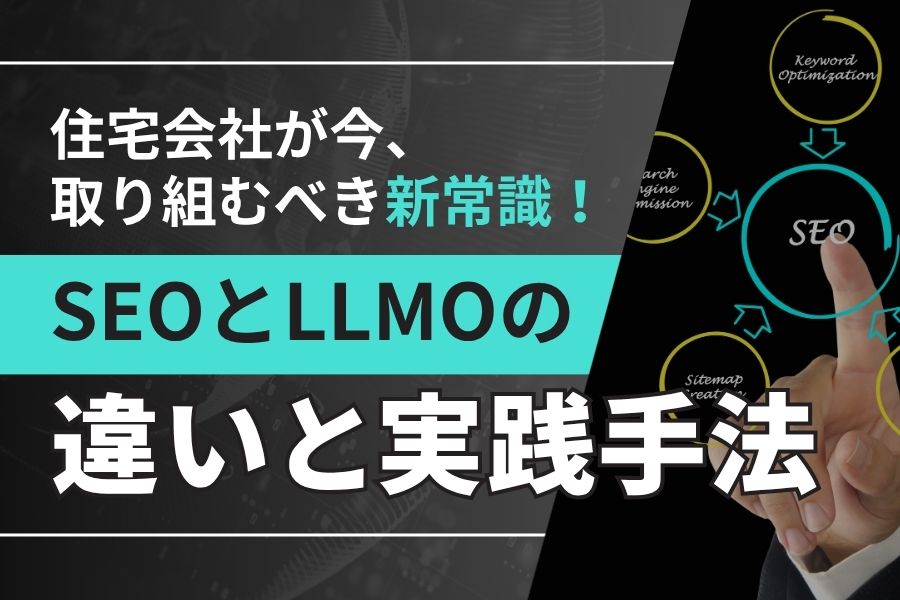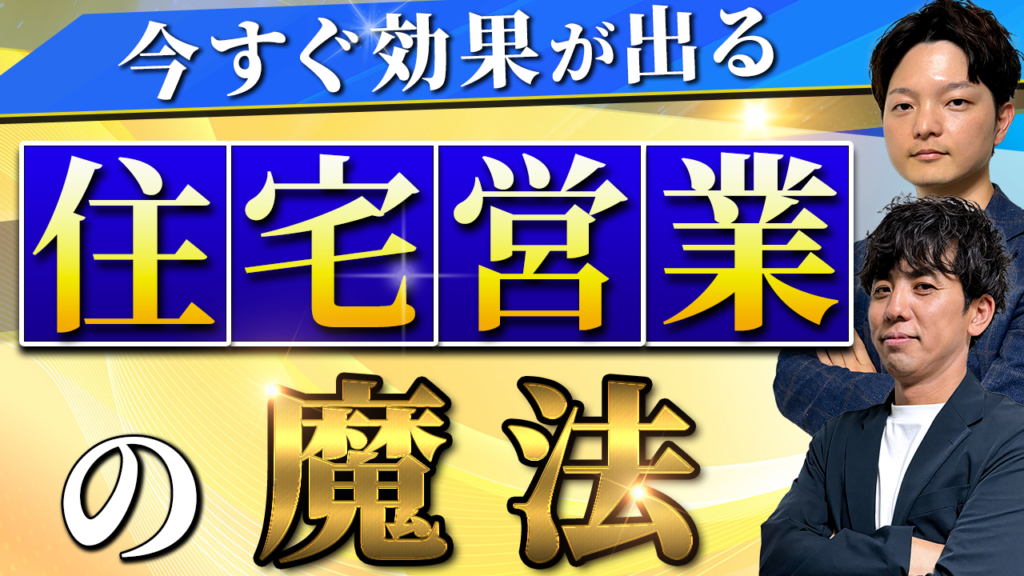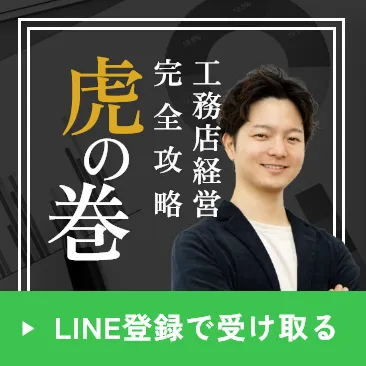歩合制だけに頼らない住宅業界の人事評価と組織づくり
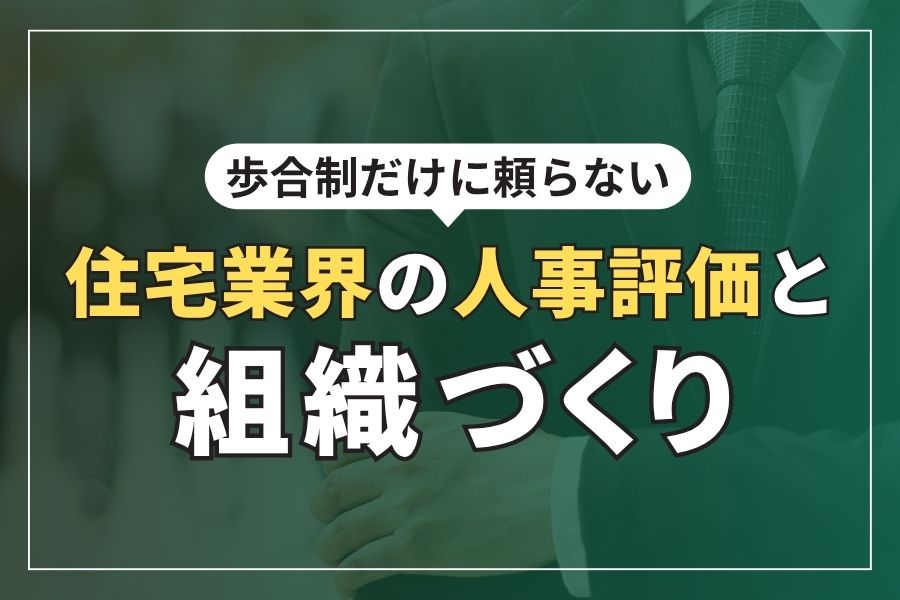
皆さんこんにちは。
ウィズモーの小倉です。
今回は住宅業界でなぜ今、人事評価制度の見直しが必要なのかを解説していきます。
歩合制だけに頼っていると利益が残らず、組織も育ちにくくなります。
これからの時代に合う、会社全体が強くなる仕組みを一緒に考えていきましょう。
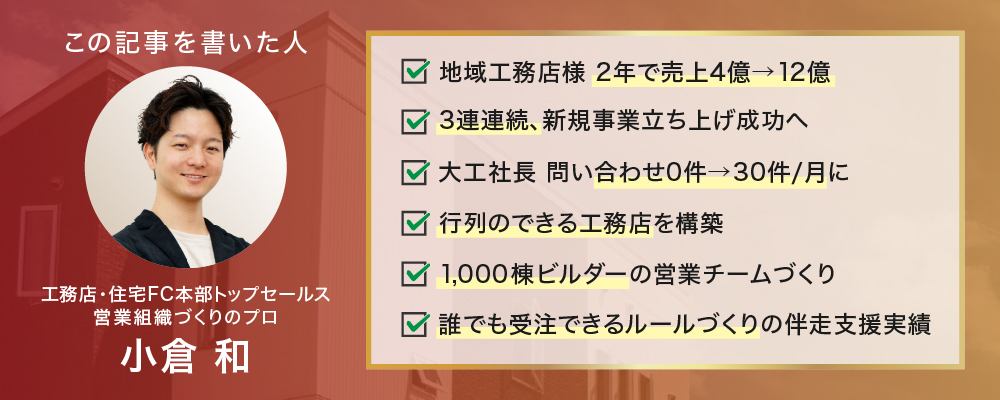

【目次】
・住宅業界で今、なぜ評価制度の見直しが必要なのか
・営業の歩合制度が広まった理由とその限界
・労働分配率から見る住宅業界の収益構造
・評価制度は本当に必要か?経営規模による必要性の違い
・これからの住宅業界で必要な人事制度とは
・まとめ
関連動画はこちら ▼
住宅業界で今、なぜ評価制度の見直しが必要なのか
住宅業界では、いま人事評価制度を見直す必要が高まっています。
これまで多くの工務店や住宅会社は、営業が契約を取ることで会社を支えてきました。
そのため歩合制を取り入れ、契約を取れば取るほど給料が増える仕組みにして、営業のやる気を引き出してきました。
この制度はとても分かりやすく、経営者にとっても管理しやすい方法でした。
ただ今は、家を建てたいお客様の動きが変わってきています。
インターネットで下調べをするのが当たり前になり、ホームページやSNSを見てから問い合わせをする方が増えました。
紹介や口コミで自然にお客様が来ることも多くなっています。つまり営業だけの力で契約が決まる時代ではなくなり、会社全体のブランドや集客の仕組みが契約につながる割合が大きくなっているのです。
この状態で昔と同じ歩合率のままだと、営業の給料が高くなりすぎたり、設計や工務とのバランスが崩れたりする恐れがあります。
チームで家をつくる仕事なのに、給与面で不公平感が出ると職場の雰囲気が悪くなることもあります。
また、人件費が膨らんで会社に利益が残らず、経営を圧迫するケースも増えています。
人事評価制度は、会社がこれから先も安定して成長していくための大事な土台です。
古い仕組みをそのままにしておくと、利益が減るだけでなく、社員のやる気やお客様へのサービスにも影響が出かねません。
これから住宅を建てる人が少なくなると言われる中で、歩合制を見直し、会社全体が強くなる仕組みをつくることが重要です。
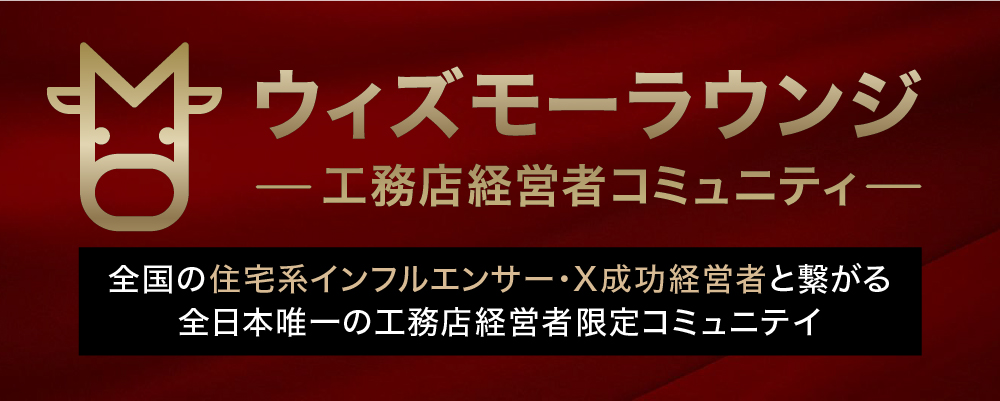
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎
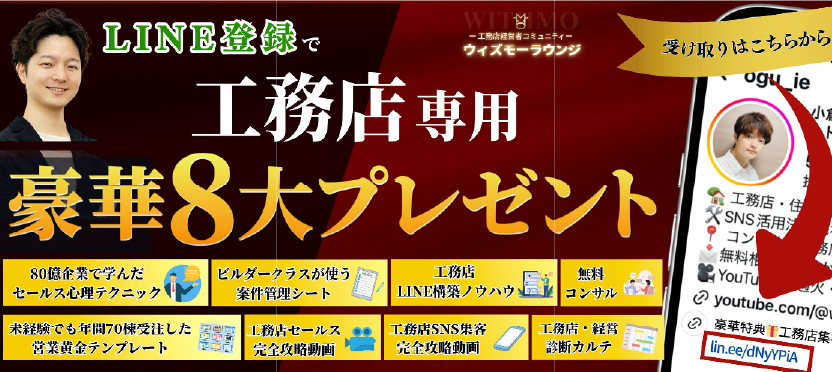
営業の歩合制度が広まった理由とその限界

工務店や住宅会社では、営業の歩合制度を長く使ってきました。
これはとても分かりやすい仕組みで、営業の頑張りをしっかり評価できるものです。
ただ最近は、この制度だけに頼るのは難しくなってきています。
なぜ歩合が広まったのか、どこに限界があるのか、順番に見ていきましょう。
契約を取った分だけ給料が増えるから
営業の仕事は、家を建てたいお客様に何度も会って話を聞き、その家族に合った提案をして契約まで進めることです。
とても時間がかかりますし、たくさんの努力が必要です。
歩合制度は、その契約が取れれば取れただけお給料が増える仕組みです。
だから営業は「もっと契約を取りたい」と自然に頑張るようになります。
目標を数字で示しやすく、成果がすぐ自分に返ってくるのでやる気につながりやすいです。こうしたシンプルさが多くの会社で採用されてきた理由です。
社長にとっても管理しやすかった
歩合制度は、社長や経営者にとっても大きなメリットがあります。
営業が契約を取れば売上が入り、その分を歩合として払えばいいので、人件費を利益に合わせてコントロールしやすいのです。
会社としてもリスクを抑えられ、無理に固定給を高くしなくても済みました。
また営業が数字を意識して動くので、細かく管理しなくても自分から行動してくれるという期待もありました。
こうして歩合制は、営業の動きを会社全体の売上に直結させる道具として広まったのです。
今は会社のブランドや集客が強くなった
ここ数年で状況は大きく変わりました。
インターネットが普及し、家を建てたい人は最初から営業に会いに行くのではなく、まずスマホやパソコンで情報を集めます。
ホームページを見たり、SNSやYouTubeで実際に建てた人の口コミを探したりして会社を選ぶ人が増えています。
これまで営業が足で稼いでいた部分を、会社のブランドや集客システムが支えるようになりました。
もちろん営業の力も必要ですが、契約が決まるまでに占める営業の貢献度は昔より下がっているとも言えます。
営業ばかりに歩合を払うのは難しくなってきた
こうなると、昔と同じ歩合の比率で営業にお給料を払っていると、他の部署とのバランスが悪くなってしまいます。
家づくりは営業だけでなく、設計や現場監督、職人さんなど多くの人が協力して進めるものです。
営業だけが高い給料をもらうと、設計や工務が不満を持つこともあります。
それだけでなく、歩合が大きいと営業はどうしても自分の契約を優先しがちです。
新人を育てたり、他の部署としっかり連携したりするより、自分の数字を追うほうに気持ちが向きます。
これでは組織として力がつきにくくなってしまいます。
歩合制度はとても便利で、これまで会社を成長させる大きな支えになってきました。
ただ今は、会社全体のブランドや集客が力を持ち、家を建てるお客様の探し方も変わっています。
歩合だけに頼るやり方では限界が見えてきました。
そこで最近は、歩合だけでなくチームで成果を分け合う仕組みや、営業のプロセスも評価する制度を取り入れる会社が増えています。
歩合の良い部分を残しながら、会社全体がもっと強くなるための制度を考える時期に来ているのです。
関連動画はこちら ▼
労働分配率から見る住宅業界の収益構造
住宅業界の会社がお金をどのように使っているかを見るとき、よく使われるのが労働分配率という数字です。
これは売上のうちどれくらいを人件費に使っているかを表したものです。
たとえば売上が1000万円あって、給料やボーナスなどに500万円使っていたら、労働分配率は50パーセントという計算になります。
中小の工務店は、だいたい50パーセント前後のところが多いです。
つまり、売上の半分は人件費に消えてしまう計算です。それに対して、年間100棟以上の家を建てるような大きな会社では、30パーセントくらいのところもあります。
売上に対して人件費の割合が低いので、同じ金額を売り上げても会社に残る利益はずっと多くなります。
福岡のある住宅会社は、まだ年間100棟ほどしか建てていない頃に思い切って人事制度を見直しました。
歩合制を変えて、労働分配率に上限を決めたのです。
これで売上が増えても人件費が増えすぎない仕組みができました。その後この会社は500棟以上を建てる規模にまで成長しましたが、役員報酬や福利厚生費を除いた労働分配率は20パーセントを切っています。
利益をしっかり残せる強い会社になれたのです。
一方で、同じように家を100棟以上建てていても、歩合制のままで分配率が40パーセントから50パーセントの会社もあります。
こうなると利益がほとんど残らず、次の投資に回せません。結局、成長できるかどうかは、どのタイミングで労働分配率を意識した仕組みを作れるかにかかっています。
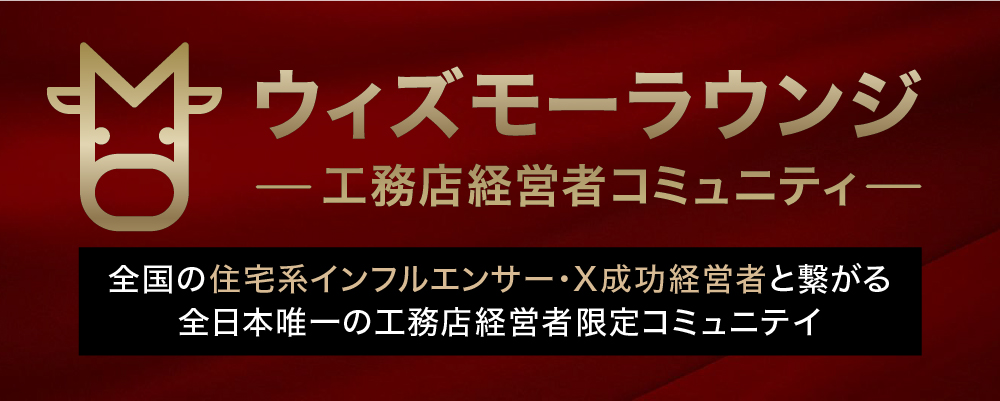
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎
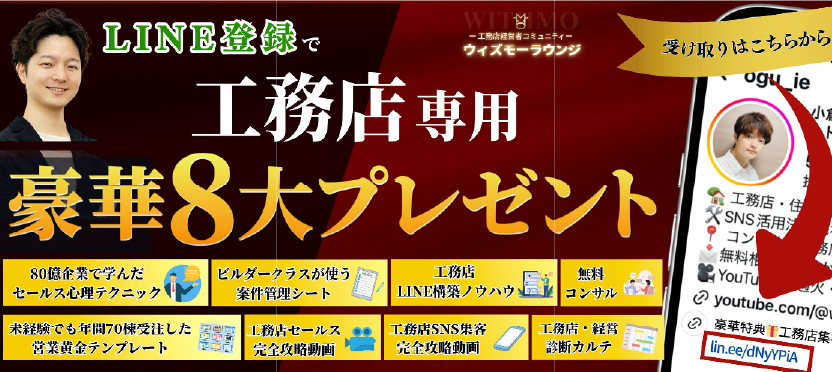
評価制度は本当に必要か?経営規模による必要性の違い

評価制度は、社員のお給料やボーナスを決めるだけでなく、会社がどんな働き方を大事にしているかを伝える役目もあります。
ただ必要かどうかは会社の規模によって少し変わってきます。ここでは小さな会社と大きな会社に分けて説明します。
小規模の会社は社長の目で十分なことが多い
社員が20人や30人くらいまでの会社は、社長がいつも社員の仕事ぶりを近くで見ています。
だれがどのくらい頑張っているのか、どんなふうにお客様とやり取りしているのかもわかるので、細かい評価制度を作らなくてもお給料やボーナスを決めやすいです。
むしろ紙の評価表に数字をつけるより、社長の目で見たほうが「よく見てくれている」と社員も安心します。
実際に小さな工務店や住宅会社では、社長が直接話をして決める形を取っているところが多いです。
大規模の会社には評価制度が欠かせない
社員が増えて50人、100人となってくると、社長一人で全員の仕事を細かく見るのは難しくなります。
そうなると、社員は「どのくらい頑張ればどれだけ評価されるのか」が分かりづらくなります。
せっかく一生懸命やっても「思ったほど給料が上がらなかった」と感じたり、逆に「何をやっても同じだからこれでいいか」と手を抜いたりするかもしれません。
会社がもっと大きくなっていくには、どんな行動を大切にしているかを社員にしっかり伝える必要があります。
評価制度があると、会社が求めている働き方や成果が見えるので、みんなが同じ方向を目指しやすくなります。
これからの住宅業界で必要な人事制度とは
これからの住宅業界では、ただ家を売ればいいという時代ではなくなってきています。
インターネットでいろいろ調べるお客様が増え、家を建てる会社を選ぶ基準も変わりました。
会社のブランド力や紹介、口コミで選ばれることが多くなり、営業だけが頑張れば契約が取れる時代は終わりつつあります。
これまでのような歩合制度だけに頼った仕組みでは、営業は自分の数字を優先しがちです。
後輩を育てることや他の部署と協力することがおろそかになると、組織としてはなかなか大きく成長できません。
そこで必要になるのが、歩合制の良さを残しつつ、プロセスや育成、チームでの成果も評価する人事制度です。
たとえば店長が部下を育てたり、設計や工務としっかり連携してプロジェクトをスムーズに進めたりしたことを評価する仕組みがあれば、営業だけの力ではない会社全体の強さが育っていきます。
給与だけではなく、表彰や感謝の言葉を伝えるなど、お金以外でやる気を引き出す方法も大切です。
社員が会社の理念や方針を理解して、自分の仕事に誇りを持てるようになると、自然とチーム全体の力が上がっていきます。
人口が減って家を建てる人が少なくなるこれからの時代、全員で協力しながらお客様に選ばれる会社を目指すには、人事制度を工夫していくことが欠かせません。
長く成長し続ける会社になるには、今このタイミングで仕組みを見直すことが大切です。
関連動画はこちら ▼
まとめ
住宅業界はこれまで営業の歩合制で成長してきましたが、ネットやブランド力で集客する時代になり、営業だけの成果とは言えなくなっています。
歩合に頼ると設計や工務とのバランスが崩れ、チームが育ちません。利益が残りにくくなる問題もあります。
小規模なら社長の目で十分ですが、大きくなると評価制度が必要です。
これからは営業の数字だけでなく、育成や連携を評価し、表彰や感謝も取り入れた人事制度が大切です。
全員でお客様に選ばれる強い組織を作る時期です。

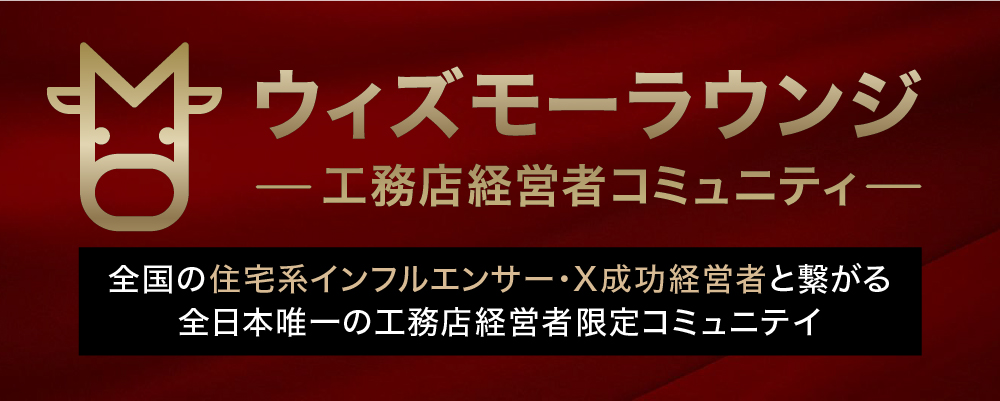
\ 無料工務店経営者コミュニティ /
✔︎最新のSNS集客ノウハウ ✔︎LINE構築の裏側 ✔︎住宅インフルエンサーとの交流 ✔︎20棟販売した住宅営業のヒミツ ✔︎入会者限定の動画コンテンツ
無料参加はこちら ▶︎